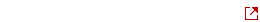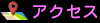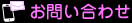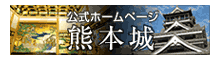わくわく座館内表記
1階ロビー
熊本城宇土櫓ミニチュア
この宇土櫓は、平成29(2017)年12月に熊本市現代美術館 CAMKで開催された「熊本城×特撮美術 天守再現プロジェクト展」で展示されていたものです。熊本地震からの一日も早い復興の願いをこめて、熊本市へ寄贈されました。制作監修者は、『進撃の巨人』や『シン・ゴジラ』などの特撮美術を手掛けた三池敏夫監督です。1/20スケールの迫力ある作品となっています。
下見板(もぎりブース横)
宇土櫓の下見板を実寸で再現しています。
★下見板とは…
城郭の初期段階に多く見られた外壁で、漆喰を用いない板張の壁のこと。板の下部を重ねて張っていき、板が下を向いているので下見板張と呼ばれる。時が移るに従って、「下見板張」→「壁上部漆喰・下部下見板張」→「全面漆喰」というように移っていったが、漆喰は雨に弱く、塗り替えを頻繁に行わなくてはならないため、時が移っても下見板張りを用いた城も多い。
1階展示室
熊本城以前の合戦と熊本城と茶臼山
-
-
加藤清正が肥後熊本に入国するまでに起こった合戦や、熊本城築城以前に存在した隈本城と千葉城について紹介しています。
〇500年ほど前、熊本は「隈本」と呼ばれ、菊地一族の出田秀信が支配をしていた。秀信は茶臼山のふもとに千葉城を築いた。
〇文明17(1485)年、出田秀信が破れ、代わって鹿子木親員(寂心)が隈本に入り、茶臼山の西南部に新たに隈本城を築く。
〇天文19(1550)年、城親冬が隈本城の城主となる。天正6(1578)年、「耳川の戦い」において島津氏(薩摩)が大友氏(大分)に勝利した。九州各国の豪族(国衆)が力を持つ時代になった。
〇豊臣秀吉の九州平定により肥後は治められ、佐々成政が領主となった。
〇隈部親永ら各地の豪族による国衆一揆が起こったが、豊臣秀吉により鎮められた。秀吉公は新たな領主として加藤清正を任命。
〇清正公は「隈本」を「熊本」に漢字表記を改めた。
〇隈本城は現在の第一高校(古城)、千葉城は元NHK(千葉城町)辺りにあった。地名にも名残が残る。
〇茶臼山は標高50mほどの丘。東の坪井川と西の井芹川に挟まれている。南に二つの川が合流する白川が流れている。
〇かつては熊本城の南側を大きく北に蛇行した白川が流れ、その途中に坪井川と考えられる河川が合流していた。千葉城はすぐ南で蛇行していた白川にあった船着場(船場)からついた名前で、元は「せんば」城、「千葉」の字は当て字ではないかといわれている。 -
熊本城被災・復旧プロジェクションマッピング
平成28(2016)年、熊本地震発生時の熊本城の石垣の崩落や櫓の倒壊の様子を、音と映像で体感できます。
1/100スケールの熊本城の立体模型に、熊本地震が起きた「その時」の状況を再現した映像を約6分間投影します。専門家の監修の元、落ちてしまった瓦や石垣の位置から、映像を作り上げました。最後に復旧のイメージも投影されます。見る位置を移動しながら、様々な角度でご覧ください。
※動画での撮影はお控えいただいておりますが、写真撮影は可能です。
-
熊本城定点ライブカメラ
熊本城内4台と熊本市役所の屋上に設置しているカメラから、生中継の映像を配信しています。熊本城の復旧作業の様子をご覧ください。
※写真や動画撮影はご遠慮頂いております。
-
石垣技術体験
熊本城の石垣を模したパズルです。石垣の積み方を実際に体験できます。
熊本城の石垣は2種類あり、年代によって形が異なります。
左側が穴太積で、石垣の角をみると、同じサイズの石が積み上がっているのが分かります。熊本城を作る際に、最初に使われた積み方です。
右側が算木積です。レンガ型の石を縦横交互に入れこんでいるため、積み上がった時角の幅が長い短いとなっています。穴太積よりも新しく、改良された積み方です。
熊本城の石垣は武者返しと呼ばれ、とても有名です。上にいくにつれて角度が高くなるので、敵は登れずに落ちてしまいます。なお、今でもこの2種類の石垣は熊本城に残っています。2種類の石垣の勾配を比較してみてください。 -
大天守屋根の瓦
熊本地震(2016年)の前震と本震の2度にわたる地震で、天守の最上階付近から落下した瓦です。天守は昭和34(1959)年に復元工事が始まり、昭和35(1960)年に竣工しました。復元にあたり、市民からの寄付金を募るため「瓦募金」が行われました。集まった金額は不明ですが、復元に使う瓦の種類ごとに募金額が異なっていました。瓦の裏面には住所と氏名が墨書されています。展示物の中には、地震で壊れてしまった鯱の尻尾の破片もあります。
-
矢穴のある石
重さ:およそ700kg 縦62cm×横78cm×奥行72cm
熊本地震で崩れた元太鼓櫓の石垣の石です。石の真ん中にある穴は、岩を割るための「矢穴」です。ここに、鉄でできた道具を打ちこんで岩を割っていました。しかし、この穴は使われていません。石には、「497」という数字があります。この番号は、平成6(1994)年の石垣の石を積みなおす工事のときにつけられました。
人の顔がかかれた石
重さ:およそ250kg 縦47cm×横58cm×奥行65cm
熊本地震で崩れた石垣の石です。石の真ん中には、らくがきのような人の顔と体が描かれています。これは、石工さんが「これからもずっと丈夫な石垣でありますように」という願いをこめて描いたものではないかと想像されます。
-
熊本城被災映像
平成28(2016)年、熊本地震が発生した年に撮影された城内の被災映像を、繰り返し上映しています。2本立てになっており、上映時間はそれぞれ10分間です。
1本目は地震の1ヶ月後に撮影された城内全体の被災の様子、
2本目は同年9月~11月に撮影された、天守閣・本丸御殿・宇土櫓の内部の様子になります。※動画撮影はご遠慮頂いております。
-
加藤清正と背比べ
加藤清正と背比べをする事が出来ます。清正公は身長が約190㎝あったと言われていますが、実際は165㎝くらいだったようです。トレードマークの長烏帽子形兜を被ることで、実際の身長よりも大きく見せていたのかもしれないですね。
加藤清正の生涯
加藤清正が生まれてから亡くなるまでの50年の生涯と、亡くなってから加藤神社に祀られるまでを年表形式でわかりやすく紹介しています。(清正公が何歳の時に何をしたということをまとめています。)意外と知られていない、治水事業などの紹介もあります。
-
参勤交代模型
熊本のお殿様が江戸に行く様子を模型にしています。120体ほど人形がありますが、実際は2,000人以上の人が江戸まで行っていました。
ケースの中の人形を見ていくと、お殿様が乗っている駕籠があります。中を覗くとちゃんとお殿様が座っています。また、お殿様を守るようにして人が配置されています。
【見つけてみよう!】
行列先頭のふさふさした槍:毛槍といいます。武器ではなく各藩のマークです。この毛槍は各藩でデザインは違っていて、これを見た人たちが「あ、○○藩が来ているな」ということが分かるようになっています。椅子:首から四角いものをかけている人がいます。お殿様専用のイスです。お殿様はずっと駕籠に入っているので、休憩のため外に出たときにこの専用のイスで休憩していたのかもしれません。
茶坊主:行列の中で一人だけ丁髷が付いていない人がいます。この人は茶坊主と言ってお殿様のためにお茶を出す人です。お茶をたてる人がいるということはお道具箱も持っていっていました。これを茶弁当箱と言ってお茶をたてるのに必要な道具が入っていました。
★参勤交代とは…
参勤交代とは、幕府(政府)が置かれている江戸と自身の領地を隔年ごとに居住する制度のこと。道中の宿泊費や移動費、国元と江戸藩邸の両方の維持費など、その経済効果は非常に大きいものであった。加藤家の後に熊本を治めた細川忠利は、参勤交代の規定について意見を述べている。意見の中で、交代時期の明確な設定を求めており、3月の交代を提起している。要因の1つとして、西国・熊本にとって海上の波静かな時期となり海路で大阪に向かうのに適しており、雪の降る東国は雪解けを待って江戸に行けるため。制度が定められてしばらく経つと、負担額の軽減がなされていく。 -
参勤交代駕籠
当時使われていたものとほぼ同じ駕籠があります。乗って写真撮影もできます。
お手軽なりきり体験
お姫様の打掛やお殿様の陣羽織を着るコーナーです。服の上から簡単に着ることができます。お姫様やお殿様になりきってみてください。※撮影はご自身のカメラでお願いします。
※衣裳は具体的な武将やお姫様の装束を元に作られたものではありません。
細川文化パネル
(上部にある大きな2枚の絵図)
花畑屋敷という細川家のお殿様が住んでいたお屋敷を描いたものです。お城がお殿様の住まいだと思われている方が多いかと思いますが、細川家の時代になるとお城は儀式に使われ、現在のサクラマチ熊本あたりに存在したこの花畑屋敷で暮らしていました。絵は幕末の御用絵師 杉谷行直(すぎたに・ゆきなお1790-1845)によるものです。(花畑屋敷図の下の各写真)
ここに上げられている数々の品は細川家伝来の品で、現在は公益財団法人永青文庫などで管理されています。花畑屋敷から発信された細川家の文化がこれらから伝わってきます。細川家の至宝は、熊本県立美術館の細川コレクション永青文庫展示室でもご覧いただけます。(令和7(2025)年3月31日まで設備調整のため閉室)★永青文庫とは…
細川家は、今日に至るまでお茶やお花、お能などの文化活動に熱心で、細川家を中心として熊本の武家文化は大いに栄えた。
細川家伝来の品々と細川護立氏のコレクションが収蔵された公益財団法人永青文庫は、東京都目白にある。(熊本県立美術館に展示室あり)
花畑屋敷の総面積は14765坪。加藤清正公が慶長15(1610)年に造営。細川忠利が寛永13(1636)年に肥後藩の国許屋敷と定め、以後藩主の生活の場となる。
明治4(1871)年には鎮台が置かれ、陸軍施設として活用。現在の花畑公園はお屋敷の一部で、公園内の大楠は江戸時代の絵図にも描かれている。馬術体験
実際に馬に乗ることが出来ます。江戸時代のお殿様はこのように大変美しい飾りをつけた馬に乗っていました。現在私達が見ることのできる馬はサラブレット、外国種の大きな馬ですが、日本古来の在来種はこのように体が割に小さく、ボテッとした印象の馬が多かったようです。
-
西南戦争立版古
動く立体紙芝居です。上映時間は約5分です。西南戦争について、熊本城炎上を中心に概要を学べます。
※音声は日本語のみ。
★西南戦争とは…
〇明治10(1877)年に起こった、日本国内最後の内戦
〇西郷隆盛率いる薩摩軍と明治政府の戦い
〇熊本城も戦いの舞台となり、熊本・大分・宮崎・鹿児島を転戦
〇火力を武器とする、本格的な近代戦
〇およそ7か月にわたる戦いの末、西郷隆盛の自刃で終幕明治10(1877)年2月14日、大雪のなか、西郷隆盛率いる薩摩軍は東京へ向け鹿児島を出発した。薩摩軍と政府軍は熊本城でぶつかる。2月19日午前11時ごろ、熊本城から突然の火の手があがる。本丸御殿や大小天守閣など多くの建物を焼失。火災の原因は、失火、政府軍による戦略上の自焼、薩摩軍による放火など諸説あって、いまだ謎に包まれている。2月22日、薩摩軍は桐野利秋の指揮のもと熊本城総攻撃を開始。政府軍は砲撃でこれに応戦。熊本城一帯はたちまち戦火に見舞われまる。薩摩軍の猛攻に耐え、城は50日余りに及ぶ籠城戦に持ちこたえた。
-
キミも変身
政府軍と薩摩軍を選んで写真が撮れます。QRコードで画像のダウンロードが可能です。
(アップロードに時間がかかる場合があるため、画面を撮影することをオススメします)火消ゲーム
火の位置に、レバーで金蔵くんを左右に動かして、赤いボタンで放水します。
右上のゲージが満タン時に放水した方が勢いよく水が出ます。西南戦争クイズ
初級編と上級編があります。西南戦争にまつわるクイズがランダムに登場します。
子どもは初級編がおすすめです。
(このクイズは、日本語表記のみです) -
対局クイズ
熊本にゆかりのある加藤清正・宮本武蔵・夏目漱石・横井小楠・細川家に関するクイズです。
(このクイズは、日本語表記のみです)熊本城本丸御殿復元模型
熊本城内の「本丸御殿(ほんまるごてん)」を100分の1の大きさに縮尺した模型です。
現在、本丸御殿は、平成28(2016)年の熊本地震の影響で、建物内の見学はできません。寸劇・アニメーションに登場する人形
2階で上映している物語に登場する人形たちを展示しています。物語を撮影した時に、実際に使われました。物語は全部で6つあり、演目によってそれぞれ異なるキャラクターが登場します。
-
年表パネル
加藤清正による熊本城築城以前から、西南戦争でお城が燃えるまでを時系列で紹介しています。
2階ものがたり御殿
熊本城VR(バーチャルリアリティ)『不落の名城を読み解く』
この映像では、江戸時代中ごろの熊本城が立体的に再現されています。鳥の目線やお殿様の目線になって熊本城を見ることができます。熊本城がいかに戦に強い城であったのか、様々な仕掛けに注目しながらお楽しみください。
*加藤清正公は「清正公さん」と呼ばれ、今もなお親しまれています。熊本城は、加藤家2代の後、約240年間細川家によって治められてきました。そのあと、明治時代になると西南戦争の戦いの舞台となり天守をはじめとする大部分の建物が失われてしまいました。現在の天守や本丸御殿は、再建・復元された建物です。
熊本城バーチャルリアリティでは、江戸時代に描かれた絵図や様々な方からの助言を基に、江戸時代中ごろのお城の姿を再現しました。
熊本城VRガイド
熊本城VRの映像を使いながら、熊本城特別見学通路の見どころをスタッフがライブ解説します。10分ほどのお時間です。熊本城の見学前にぜひご覧ください。
寸劇・人形劇(アニメーション)
熊本の歴史をアニメーションやお芝居で紹介します。物語は全部で6つあり、演目によってそれぞれ異なるキャラクターが登場します。
よみがえる熊本城(パネル)
熊本城は自然の地形を取り入れた周囲5.4㎞に及ぶお城です。白川・坪井川・井芹川などを内堀・外堀に利用し、場内は空堀(水の入っていない堀)として利用した要塞となっています。城内の石垣も400年変わることなく曲線の美しさを伝えています。熊本城は天守閣以外にもたくさんの建物がありましたが、明治10(1877)年の西南戦争において多くの建物が焼失しました。天守閣は昭和35(1960)年に再建されて、その後も保存修理が続き、平成20(2008)年に本丸御殿大広間も復元されました。
はさみ箱
外出する時に、衣類や調度品などを入れる箱です。殿様の従者に持たせました。形は四角形で蓋がついており、棒を蓋に通して肩に担ぎました。名前の由来は、昔は竹に衣服を挟んで運んだために「はさみ箱」と名前が付きました。大名行列では先頭を行くため「さきはこ」とも呼ばれています
十三幡連馬験
戦国時代に大部隊での戦いが多くなったことで使用されました。戦いでは大将の馬のそばに立てて、場所が分かるように目印として利用されました。幡(布の部分)には加藤清正の「家紋」「蛇の目紋」が描かれています。
四斤山砲 1門
江戸幕府がフランスから買った大砲を「薩摩藩」が国産化したもので、「西南戦争(1877年)」のときに政府軍・薩摩軍が使用したものです。「4斤」とは大砲の弾の重さが4㎏あるという意味です。持ち運びができるように取り外しができます。
レゴブロックの熊本城
平成28(2016)年4月に起こった熊本地震により被害を受けた熊本城の復興を願い、「ツーリズムEXPOジャパン」の会場にて熊本城をレゴブロックで製作したものを展示しています。作ったのは「三井淳平」さん。レゴブロックの会社から認定されたプロの「レゴビルダー」です。字が書いてあるレゴブロックは、会場で販売されたレゴブロックに応援メッセージを書いて積み上げられたものです。一般の方をはじめ、観光関係者の方、日本の国会議員の方が書かれたそうです。
*「ツーリズムEXPOジャパン」
世界各国の魅力などを展示やステージ・グルメなどで紹介する「世界最大級の旅の祭典」。世界140の国と地域と日本の各地の「旅」の最新情報を伝える。
-